2016.11.4
《Review》NEWCOMER SHOWCASE #1平原慎太郎振付作品
REPORT2016.11.4
《Review》NEWCOMER SHOWCASE #1平原慎太郎振付作品
REPORT
「路上で思考するダンス」
国内ダンス留学@神戸5期生 NEWCOMER SHOWCASE #1
平原慎太郎振付作品『Four pieces for you』
(text by 竹田真理)

今年から新たに各講師による振付作品のクリエイションの課程が設けられている国内ダンス留学@神戸。そのショーイング公演【NEWCOMER SHOWCASE】の第一弾を見た。講師はこの8月にトヨタコレオグラフィーアワードの最新の、そして最後の受賞者となった平原慎太郎。この日のために過去の振付作品からシーンを集め、1時間に構成したものを上演した。
現在、平原は精力的に仕事をしていて、月に一作のペースで新作を作っているのだという。上演された『Four Pieces for you』はその勢いのままに、引出しから次々とアイデアを取り出してくるような多彩さが魅力の作品だった。出演は5期生全員の11人。人数を生かした群舞は見応えがあり、ダンサーの配置によって舞台を重層的に構成していく平原の手腕が光る。ユニゾンで動く全体から個別の関係にフォーカスし、コンタクトを用いたデュオやトリオ、床を使った動きなどスリリングなシーンが続く。動きは日常的だが、時折ハッと目を引くオリジナリティある振付が散りばめられているのが、見ていて新鮮だった。ただ動きのまとうニュアンスは決してハッピーではない。複数の作品からのピックアップであるから一貫したテーマはないのだが、今の日本が抱える負の側面を見るような暗いトーンが全体を覆っている。11人が舞台をばらばらに行き来する姿は都市のアノニマスな人の群れを思わせる。コンタクトから起こす動きは鋭く、敵対的で、理由のないまま振るわれる暴力にも見える。無機的な群れの中、偶発的な接触が暴力に転じる様は、そのまま社会の中のディスコミュニケーションを描くようでもある。

冒頭、まだ客電も落ちないうちに、男がひとり舞台を歩き回っている。実はこの“歩き”の様子に、初っ端から引き込まれてしまった。どこへ向かうともなく徘徊するダンサーは、何かを探しまわるでも、「ここはどこ?」といぶかし気に演技するのでもない。抽象的な運動としての歩行でもない。そのすべてを含んでそこに居るような、存在することと同義であるような歩きなのだ。アフリカのパーカッションにコーラスの混じる民族調の音楽が人類の来し方を想像させ、一人の若者の歩く姿が、普遍的でニュートラルな身体像を提示している。
この冒頭の身体に着目して作品をあらためて眺めてみると、ここから逸脱し、ある特異な方向へと特化した身体像が様々に投げ込まれていたことに気付くだろう。平原の言葉を借りれば「身体の動きが停止する状態」が探られる。死と生、動物と人間、モノとからだといった対照の中に、身体とそうでないものの境界を探り、その向こう側にある身体の像を探る試みである。たとえば「物体」と化した身体を思わせるのは、床に並んで伏した二つの体。その一人の手や足を3人目のダンサーが持ち上げたり離したりしていると、どうしたわけか、いじられていない方のダンサーの手足が勝手に上がり下がりし始める。連結した機械のような反応が可笑しく、ちょっとネタ的なシーンでもあるが、意思や衝動もなく作動するそれは、身体なのか物体なのか機械なのか。
スクリーンの前を11人が一列になり上手へ向かって歩くシーンは、人類の進化の図を思わせた。直立歩行する先頭のダンサーから次の人へと順に姿勢を歪めてゆく図は、後方のダンサーになるにつれ、腰の曲がった老人にも、霊長類にも見えてくる。進化の図を逆にたどり、ヒト以前の段階が、あるいは「退化」が視覚化されるのである。最後の一人はほぼ前屈し、体を極端にたわめた歪(いびつ)な歩きになる。思考上の身体像だが、見るのは少し恐ろしかった。

或いは、「人形」としての身体。左右に開いた手足で‘やじろべえ’のように体を揺らすダンサーは、機械仕掛けの壊れたフィギュアのようだ。このダンサーは以後、たびたび現れては、やじろべえの動きを甦らせる。オブセッショナルに反復される記憶のように、不気味な感触がひたひたと作品を浸していく。
後半はこれらの特異な身体像が続々投入され、ナイトメアのごときシーンを作って非常に見応えがあった。自分の手のひらを不思議そうに眺めている者、壁ドンする者、交わる男女。誰かが床に倒れており、片隅では何かの身振りに固執する者がいる。落とし気味の照明のもと、意識下の世界があらわになるかのように、脈絡のない欲望や悪夢のイメージが記憶の淵から取り出されてくる。やじろべえのダンサーは調子の狂ったロボットのように強迫的で、「退化」の歪(いびつ)な歩きは後ろ向きになり行進する。ダンサーたちにとっては個々の身振りの脈絡のなさを、どう自分の腹に落として踊るかがチャレンジだったようである。その点では各々が振付を誠実に受け止め、自身の言葉にするべく努めていたという印象だ。ここに振付を追い越すほどの勢いが出てくれば、さらに迫力あるシーンになりそうだと思われた。

ラストシーンに現れたのは「死体」である。死体こそは、動きを停止した究極の状態であり、身体とそうでないものを分かつ最も鮮烈な境界だ。しかしまた、目の前に並べられた動かぬ身体たちは、大災害の、或いはテロの、ジェノサイドの犠牲者であり、世界の不条理を語る累々たる屍だ。傍らに佇み見つめていたダンサーたちが、ひとり、またひとり床の「死体」と入れ替わる行為が、「これはあなたかもしれない」と語りかけてくる。世界が直面する現実にダンスで応えようとする舞踊家の姿勢が表れた場面だった。


見てきたように、作品は危機の時代を反映し、全体に暗いトーンを滲ませている。それでも平原の身体言語の根底には根本的な明るさを感じた。ダンスへの疑いや批判よりもダンスへの信頼に支えられた踊りは、コンテンポラリーダンスの展開の中では保守に位置すると言えるだろう。ただし、動きそのものに対して過度に内省することなく、技巧に傾きすぎず、さまざまな場所で踊り続けてきた平原自身の身体性に根差していて、ヒップホップの語彙を用いるのではないが、ストリートの感覚に満ちている。密室で観念的に練られるダンスではなく、路上で思考するダンス、身一つから他へと開かれるダンスである。その等身大のリアリティが、踊ることで人生に関わっていこうとしているダンス留学生たちに、そうするのに十分なだけの身体を備え、整えることを教えている。平原から5期生たちへの、これ以上ない贈り物だったろう。
(all photo by junpei iwamoto)
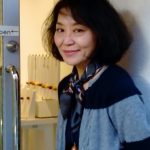 竹田真理
竹田真理
東京都出身、神戸市在住、ダンス批評。90年代半ばに舞台を見始め2000年より関西に拠点を移して活動。記者・批評歴はダンスボックスとほぼ同じ20年くらい。コンテンポラリーダンスに限った舞台評やインタビュー記事を一般紙、ダンス専門誌、ウェブ媒体等に寄稿。国内ダンス留学@神戸の第一期~4期まで選考委員を務めた。