2018.11.15
Monochrome Circus『TRIPTYQUE/三部作』インタビュー | 森裕子×隅地茉歩(セレノグラフィカ)
INTERVIEW2018.11.15
Monochrome Circus『TRIPTYQUE/三部作』インタビュー | 森裕子×隅地茉歩(セレノグラフィカ)
INTERVIEW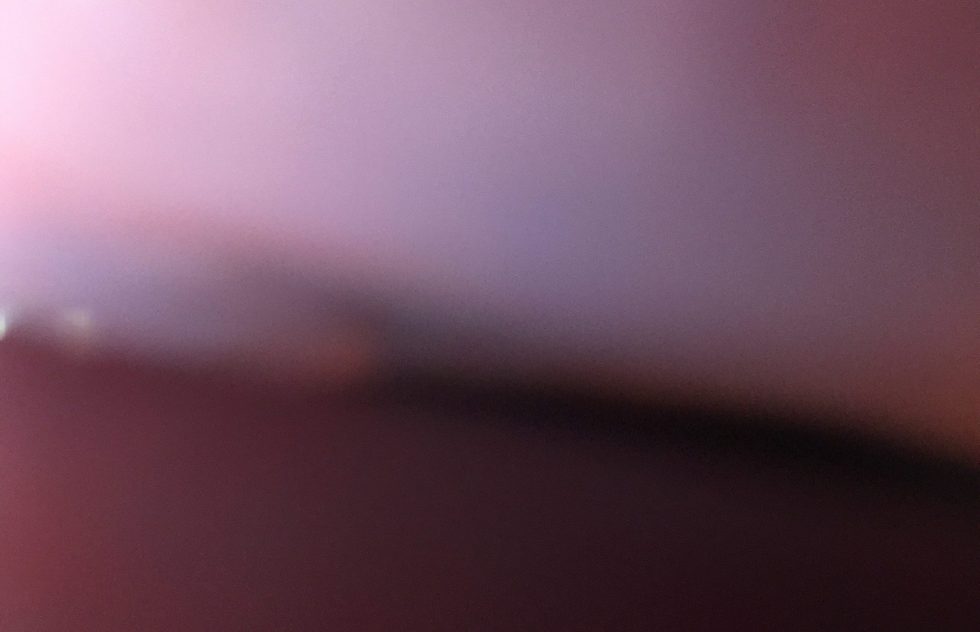
今回のMonochrome Circus『TRIPTYQUE/三部作』は、坂本公成さんと森裕子さんのデュオ三作品をリクリエイトして上演いたします。そこでデュオをベースにカンパニー活動を行なっているセレノグラフィカ・隅地茉歩さんと森裕子さんの対談を行ないました。途中、女子会のようなノリもあったり、聞き手・横堀の人生相談が入ったりと、ここに掲載できなかった対話もかなりございますが(笑)デュオであること、カンパニー活動を継続することなどを中心にお話しをお伺いしました。それでは、どうぞ!(聞き手:横堀ふみ)
森:私たちもあります。
隅地:私の場合はデュオ作品が割合としてとても多い。私たち自身のリハーサルの時は、お互いに考えていることが違ったとしても、とにかくまず見せ合うってことですね。そこからがスタートってことが多いかな。私の頭の中で出来上がっているものを、阿比留さんに踊ってもらうっていうことではなくて、なにか分からないものを拾い集めることを一緒にするって感じでしょうか。
森:最初にテーマが決まるんですか?
旧作の再演の稽古に入る時もそのような作業をするのでしょうか。
隅地:うーん…。再演の時に「ともかくじゃあ思い出しましょう」っていうだけはつまんないというか、思い出してそれを克明に再現するってことより、「今やる」ってことを確認したいんですよね。
森:私たちは再演の場合は克明にやります。あんまり変えないんですよ。
隅地:あ、私が先ほど言ったのは、変えるってことではないですよ。
森:今日ここまで行った、ああこんな早く終わっちゃったから一旦寝かしておこうという時もありますね。変更をあまりしないので、やっている身体でもう一度味わい直すというか。その日その日で感じ方は違うし、全体の時間の長さも違ってくるので調整しなおす感じですね。

ちなみに、Monochrome Circusは新作をつくるとき、どう進んでいくんですか?
森:『夏の庭』の場合は、何か決まっていたわけではないけど「コンタクトでなにか作りたい」っていう欲望があって、取り掛かり後からテーマを決めました。
『きざはし』は、その前に作った『水の家』という男女2人の作品の影響があります。『水の家』では机の上で2人が踊るんですが、その枠組みを残して「机の上と下で踊る」ということからスタートした感じですね。
『Endless』の場合は、フランスの芸術センターから即興でも何でもいいから2人で踊ってくれっていうオーダーがあって。即興で見せるのは嫌だということでつくり出しました。2人で踊るということと、その前の『HAIGAFURU』っていう核の問題をテーマにした坂本がつくった作品があるんですが、その作品を引き継いだもの。そして『HAIGAFURU』はとっても大きなテーマなので、それより自分たちの身近なテーマに引きつけていったと思います。ちょっと坂本と意見が違うかもしれないけれど。
最近、今回上演する「夏の庭」「きざはし」「Endless」の3部作の上映会をしました。その時に、坂本公成さんがテキストを書いてくださって。それによると、Monochrome Circusの作品で、公成さんと裕子さんのデュオ作品ってこの3作品だけっていう。もっとデュオの作品数があるイメージがあったのでとても驚きました。

森:あ、そう?私たちは3つで適度やねって(笑)まず2人でつくって、他の人と別の作品を作って、また2人でやるとなった時に前回の作品の影響があって、またつくって他に影響して。。。なんか、節目節目で作っていますね。
もう少し多い印象があったんです。セレノグラフィカはデュオって何作品ありますか?
森:50作品、と坂本のテキストに書いていましたね。
デュオをつくる時って、大人数の作品をつくる時よりつくりやすいものでしょうか?
森:作りにくいよ(笑)。カンパニーで作るときは坂本が演出する。演出家がいて、ダンサーがいてという形で作るので見る目があるじゃないですか。デュオを作る時、今までカンパニーのメンバーに見てもらいながら作るということもしていなかったので、2人で喧嘩しながら(笑)。
隅地:なりますよね。やっぱりそう。
森:しかも私たちってパートナーでしょ。余計やりにくい…かな。どうですか?
隅地:やっぱり、デュエット独特の逃げ場のなさというのはあるんですよね。あとは自分がつくるっていう演出の目を持ちつつ自分たちで踊らないといけない、ある種の大変さ。
森:客観性も失ったらいけないし。2人ともそれぞれに意見はあるから。
隅地:私たちの場合は結局2人から出てきた意見に基づいて進んでいくということになります。相手が納得していないことは出来ない。そうすると、最初「え?」ということだったとしても、まあ納得できる地点がどこかにあって、「じゃあ」と、そこを一緒に越えていくっていう。ところで裕子さんと公成さん、私と阿比留さんでは間柄が実際ちょっと違いますよね。本当にパートナー同士なのと、赤の他人なのではね。
森:だからその辺でいうと、カンパニーでやっているということはちょっと助かっている部分はありますよね。他の人がいるから違う息抜きが出来るというか。
隅地:いやいや、分かりますよ(笑)。でもご夫婦ってね、ちょっと違いますものね。私たちなんかは必要がなければ会わないで済む。なんていうか、あるほとぼりが来るまで放置。勝手に時間が冷却してくれますよね。
森:でも喧嘩できないとダメだしね!
隅地:絶対そう!
昨年度の下町芸術祭のときに、茉歩さんのインタビューで「翁と嫗になる腹を括った」と仰られていたんですが、それは阿比留さんと一生踊り続けるってことに対して腹を括ったということですか?

隅地:なんでしょう。もちろん阿比留さんと私の居方で踊っていくことなんだろうけど、もうそこに対する拘りから解放されたかなという感じですね、ニュアンスが難しいですけど。カンパニーになって年数が経ってきたというのもあって、一人のおじいさん、一人のおばあさんだったりするもの同士になっていくなあと思い始めてきたということですかね。そういう風な考えにちょっと変化してきたっていうことですね。
自然に踊っていくもんだという感じ?
隅地:自然に2人で踊っていくのはもちろんそう出来た方が良いだろうけども、すごい口幅ったい言い方をすれば、持っているものがもっと普遍的に、自然になっていけばいいのになっていう。2人が一緒に踊ることに、今よりももっと普遍性が出てくれば良いなあ、無名の翁と無名の嫗であれれば良いなあと思うようになりました。
裕子さんと公成さんはどうですか?Monochrome Circusを2人でずっと続けて行く、と考えていますか?
森:まだ2人になって2年目ですし、年老いていくことで2人の身体が変わっていくこと、その先を見つけたいなっという思いもありますけど、まだ描けていない。翁と嫗を目指していくのと自然になるのとは違いますよね。なんかこう、そこへ流れていく在り方が公成さんと私とでは一緒ではないだろうなと思っています。寄り添いながらいけたら良いなとは思いますけど。
歳を重ねていくこととダンスを踊っていくということはとても密接に関わり合っていることですけども、その身体でずっと踊っていくということを選ぶのか、後進の育成ということを選ぶのか分かれるように思います。
森:どっちでも良いかな。いずれにせよ、身体を見ているのは好きなので、どっちでも良いかなって思えたら良いな。踊りたい欲もあるけど、歳取ってきたらヒトの身体見るの楽しくない?
隅地:楽しい楽しい。
森:なんか、見方が変わってきたというか。前は教える時に自分ができないと教えられない、伝えられないって思っていたけど。私は出来ないけどって言いながらも、教えていいかな、この歳やったらまあいいかって思えるようになった(笑)。
さっき仰っていた身体を見るのが楽しくなったという変化はどういう風に変わってきた感じがしますか?
森:私たちはコンタクトをするので色んな人の身体を見ます。変わっていく身体が面白いっていう。変わっていこうとしているとか、変わっていく意志のある身体とか、変わっていく可能性がある身体とか。それを見るのが面白いって感じかな。
森:経験だと思う。こう伝えたらこう伝わるっていうポケットが沢山になってきている感じね。
宴もたけなわですが、、!? 話は尽きませんが、そろそろ女子会!?の終わりの時間がやって参りました。
隅地:こんなに長い時間裕子さんと話せるっていうの、私初めて。長いこと近くではいるんだけど。
森:近くにいるのに通りすぎてるっていう。
隅地:挨拶はもちろんしてるし、何回かポイントポイントで同じものに出てたりね。
森:『R-40』(※1)ね!『R-50』しようよ!R-60になる前に!(笑)

(※1)2007年 ダンスボックス・フェスティバルゲート時代に上演された即興ダンスバトル。関西をベースに活動している40歳を過ぎた男女のダンサーたちが一堂に会し、即興ダンスバトルを繰り広げた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
京都を拠点に「身体との対話」をテーマに活動を続けてきたカンパニーMonochrome Circus(主宰:坂本公成)。1990年に結成以降、国内外で活動を展開し、数多くの作品やダンサーを輩出してきた。今回の公演では[坂本公成+森裕子]という単位に戻り、この20年あまりの間に上演した、時代も背景も異なる3つのデュエットを通じて、身体への眼差しの変化を俯瞰すると同時に、新鋭のダンサー[中間アヤカと山本和馬]に振付の委嘱を行い、カンパニーの言語を次代に継承していくことも試みる。